夢のような非現実感。画面全体を彩るアートな色使い。安定のA24………じゃ、ない!!
てっきりA24製作or配給かと思ってしまいました。めっちゃ失礼ですよね、ごめんなさい。
でも、あまりにA24的(重ねがさね失礼)…というか「ラスト・ブラックマン・イン・サンフランシスコ」に通じるものがありすぎて、もうセットで鑑賞するしかないでしょうという感じです。
どちらも自分が生まれ育った場所が失われることが、若者のアイデンティティの危機につながっています。
街が変わっていく、家が失われる、とはどういうことなのか。
この映画の主人公ユーリと一緒に考えていきたいと思います。
鑑賞のまえに
2020年製作/フランス
時間:95分
監督:ファニー・リアタール、ジェレミー・トルイユ
出演:アルセ二・バティリ、リナ・クードリ、他
・タイトルからイメージされるような宇宙空間・宇宙船のイメージが美しい。
・2019年に取り壊された実在の公営団地「ガガーリン」が舞台。ジェントリフィケーションが1つのテーマです。
・A24の「ラスト・ブラックマン・イン・サンフランシスコ」がお好きな方はぜひ。きっと心に刺さります。
あらすじ
パリ郊外に実在するガガーリン団地で育った16歳の少年ユーリ。彼は宇宙飛行士を夢見ており、かつて自分を置いていった母の帰りを待ちながら、思い出の詰まった団地で暮らしていました。
しかし老朽化とパリ五輪の都市再開発によって団地が取り壊されることになり、住民たちが一人また一人と去っていくなか、ユーリは親友のフサームや、想いを寄せるディアナと協力して、団地の修理や補修を試みながら立ち退きに抗おうとしますが…
感想
建物の老朽化や都市計画により、住人たちそれぞれの願いとは関係なく公営団地が取り壊されることになるのは、ある意味で仕方ないことだと思います。
私の実家は個人のオーナーが所有する小規模なマンションでしたが、老朽化を理由にしてやっぱり跡形もなく撤去されてしまいました。住人の半分くらいは「まぁ、そんなものか」という感じで早々に新しい場所に移っていき、半分くらいは抵抗していましたが…その人数も一人またひとりと減っていき、いつかは最後の一人になります。
そうしてこの映画の主人公、偉大なる宇宙飛行士と同じ名前のユーリ少年は、公営団地「ガガーリン」の最後の住人となりました。
映画の序盤では様々なカラーの住人たちで賑わっていたガガーリン団地。実在の団地も18階建て、380戸の巨大団地だったみたいですね。名前に違わず、スケールの大きな団地。それはもはや一つの町といった印象を受けます。
唯一の肉親の母親はユーリを置いてずっと前に団地を去っていて、まだ16歳のユーリはこの団地で健気に一人暮らしを続けています。彼の両親は若い頃に事情があってこの団地に流れつき、そこからまず父親が家族を捨てて出て行ってしまい、その後に母親も恋人と暮らすためにユーリだけを団地に残していった様子。ユーリはそんな状況でも、いつかは母親が戻ってきて、またここで親子で暮らせるという願いを捨てきれていません。
家庭らしい家庭を与えられていない少年たちが、心のどこかに「温かい家庭・温かい母親」のイメージを大切に持ち続けている姿は、本当に胸を締め付けられるものがあります。
最近読んだ小説「荒野にて」(映画化もされてます)の主人公のチャーリーもそうでしたが、一見したところは同じ年頃の男の子たちよりもずっと大人びていて逞しいのに、どこかに「幼い子どものまま、成長できなかった部分」を抱えている。それはうまく隠そうとしても必ずどこかで顔を出してきて、本人を追い込んでいきます。
幸いユーリは同年代の友人たちや、母親代わりの親切な女性などが団地の中に住んでいて、さほど辛そうには見えませんでした。少なくとも団地での日常が続いている間は…。
長年の間パリ郊外で人々の暮らしを支えてきたガガーリン団地が老朽化のため(パリ五輪に向けた都市計画の見直しのために)取り壊されるという話が持ち上がったとき、住人たちのほとんどはその運命を諦めと共に受け入れているように見えましたが、ユーリには取り壊しを阻止するという以外の選択肢はありませんでした。
なぜなら16歳のユーリには、他に行くところがないから。これは「ラスト・ブラックマン・イン・サンフランシスコ」のジミーがあの美しい一軒家に固執していたのと同じ理由ですね。この広い世界で、ここ以外に自分を受け入れてくれる場所を知らない。だから意地でもそこにしがみつくのです。
もう電気系統とかボロボロで、アスベストまみれで、どう考えても高校生の力でこの巨大な建物を修復することなんて不可能だと言われても。周りに「現実を見ろよ」と言われても。たとえ母親が残していった、大切な思い出の品を売ることになっても。少年たちにもっとずっと大切なのは、「ここにいてもいいんだ」と思える居場所。自分が確かに「そこに属している」と感じられる家庭や地域の共同体のつながりです。
帰属意識。それがユーリやジミーやチャーリーのような少年たちの物語を読み解いていく鍵になるような気がします。自分の「家」を失う、生まれ育った「町」が変わっていくというのは、そこにあった家庭や共同体と自分のつながりが断たれてしまうことを意味するのです。それは、まだ何者にもなれていなくて、自分で自分の居場所を作っていくだけの力がない少年たちの心に、取り返しのつかない喪失感を与えます。
団地の取り壊しの作業が始まる前、まだガガーリン団地に人々の生活があった頃、住人たちが団地の前庭に集まって皆既月食を眺めるシーンがあります。もうこの場所が無くなってしまうと知りながらも、皆で天体ショーを楽しみ、束の間のお祭り気分を分かち合う。ユーリの仕切りで少年たちが観察用の大きな天幕を張り、その下には老若男女あらゆる人種の人たちが集まっていました。
太陽が少しずつ欠けていくのを、このときは誰もが同じ思い、今この瞬間に宇宙の神秘に立ち会っているという喜びと驚きで見つめています。
この場に立ち会った人達は、一人の例外もなくいずれは団地を去り、共同体はバラバラに散って、跡形もなく消えてしまうことになるでしょう。けれど、この瞬間に皆で空を見上げて皆既月食を見届けたのだという思い出は残るはずです。
本当の意味での「home」として、私たちが心の拠りどころにしているのは、こうした共同体の記憶や思い出なのだと思います。自分がどこかに属していると感じるとき、その核にあるのは物理的な建物ではなく、今ではもう目には見えない場所や時間です。建物は、その象徴に過ぎない……過ぎないのですが、それでも少年たちがそこに縋ってしまうのは、まだそこまで達観できていないから。それは仕方ないことだと思います。
ユーリも住人たちが続々と引越していく中で、母親から「あなたを引き取れない」という無情すぎる便りを受け取ります。ひょっとしたら母親が自分を受け入れてくれるかもという希望が断たれ、ユーリにとって恐らく一番恐れていた事実が突き付けられました。その結果、ユーリの中で決定的な何かが振り切れて、彼は最後まで一人でガガーリン団地で生きることを選びます。
人々が去ったあとの巨大な団地は、まるで一つの世界の抜け殻のよう。ユーリはそこに電灯の明かりをともし、野菜を育て、ビニールカーテンを張って、小さくも新しい住居を作ります。その空間は、宇宙船の内部そのもの。映画などで私たちが親しんでいる、宇宙飛行士たちの暮らしのようです。
想像してみると、その場所はただの見た目以上に宇宙船に近いところなのでしょう。周囲には一切人の気配はなく、抜け殻となった巨大団地が夜の中に浮かび上がっています。
それは、まるで宇宙飛行士のような孤独です。あまりに広い無音の空間に、自分一人きり。
帰属意識を奪われてしまった10代の男の子が感じるすべてが、この映画の後半の静かな時間に詰まっているように思えました。
ユーリと外の世界をつないでくれるのは、彼が思いを寄せる少女ディアナ。ディアナは彼のことを気にかけ、解体を待つ建物の中に彼が築いた不思議な世界へと足を踏み入れます。彼女がそこで見たのは、空っぽの空間に広がるユーリの夢。子どもの頃に夢見た宇宙飛行士の世界を再現しようとしたような、どこか子どもじみているけれど純粋な、美しい空想の数々でした。
周りの世界の何もかもが彼から大切な物を奪っていくから、彼は16歳の自分にできる精一杯の形で最後に残されたものを守ろうとしています。その家で母親と過ごしていた幸せな時代に、自分が部屋の中いっぱいに広げていた宇宙の空想。それはそのまま彼にとっての「home」の最後の名残なのでしょう。
けれど自分だけの空想の世界に閉じこもるほどに、周囲の世界との溝は深まっていきます。ユーリとディアナが遠く離れた場所からモールス信号でやり取りをするシーンが切ない。宇宙飛行士が地球とコンタクトをとるための、脆く頼りない通信の音を思わせます。
そしてついに訪れた、ガガーリン団地解体の夜。かつての住人たちが建物の周囲に集まって、自分たちの「家」だった団地の最期を見守ろうとしている中、不思議なことが起こります。建物の上層階の一列が、まるで本物の宇宙船のように光を明滅させるのです。
皆と一緒に団地を見上げていたディアナが、その光の意味に気づきます。「S…O…S…ユーリだわ!ユーリがまだあそこにいる!」
夢中で建物の中に飛び込んで、ユーリを探すディアナと親友のフサーム。そのときユーリの幻の中では、ガガーリン団地は解体の運命を回避するために宇宙に逃れようとするかのように浮き上がり、ユーリ自身の身体は真っ暗な無重力の闇の中に放り出されます。この世界に居場所が無いと感じて、宇宙空間の圧倒的な孤独へと落ちていくユーリの姿は、懸命に耐えてきたけれども、これまでの彼の絶望感がどれほど大きいものだったかを表していました。
母親に拒絶されて、自分を守ってきてくれた団地の共同体はバラバラになってしまった。それは10代の少年にとって、宇宙飛行士がたった一人で宇宙の闇を漂うのと同じくらい恐ろしいことです。
自分が属していたはずのものは全て失われてしまった。
「家」は永遠に失われてしまった。
その哀しさの中でもがき苦しむユーリが、必死に周囲に発したサインがモールス信号の「SOS」だったのでしょう。
もしも彼が本当に独りぼっちだったなら、そのSOSは誰にも届くことなく宇宙の暗闇の中に消えていたと思います。けれど、ユーリはちゃんとそのときにも誰かとつながっていました。ディアナが彼のSOSに気づき、フサームと一緒に彼を探しにきてくれます。そして建物から連れ出された彼を見守るのは、かつてガガーリン団地で同じ時間を過ごした人々。共同体の仲間、彼の家族です。
団地が解体されることになれば、住人たちはバラバラになり、二度と一緒に同じような時間を過ごすことは叶わなくなるでしょう。それは確かに悲しいことですし、まだ家庭の中で守られているべき10代の子にとっては大きなショックだと思います。
ですが、人が「自分はこの共同体に属している」と感じるとき、その想いの重力の中心にあるのは記憶、過ぎ去った時間、思い出の中の人々です。鉄とコンクリートの塊ではなく。思い出を共有する人たちとの関係も時間と共にやがて変化していくでしょうか、自分の記憶の中では永遠にかつての笑顔をとどめておくことができるでしょう。
それが、自分の心の中の故郷となり、大人になっても自分を支えてくれる「家」になります。映画の最後、静かに目を開けて、自分を見守ってくれる人達の姿をそこに見たときのユーリの笑顔が印象的です。その表情は、彼がその優しい真実に少しでも近づけたと、そして子ども時代を抜け出して大人へと少し成長したことを表しているのではないかと感じました。
全編を通して、地上と宇宙の狭間にいるような、静謐で美しいシーンに彩られた映画です。ユーリの空想の世界がリアルになっていくほどに、周囲には静けさが広がり、人の気配が消えていく感じに胸が詰まりました。打ちのめされると意地になって、自分の内側にこもってしまう内向的なユーリに共感できる人も多いはず。でも最後にはちゃんと救いと希望が見える物語です。
この映画を好きだと感じたら、ぜひ「ラスト・ブラックマン・イン・サンフランシスコ」や「荒野にて」も鑑賞してみてください。いずれも「家」を失った若者たちが、それでも不屈の精神で立ち上がり、世界に居場所を求めて生き抜こうとする物語です。私は彼らの姿にすごく勇気をもらいました。これらの映画を見て同じように感じられる人が、きっといると思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!

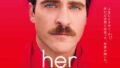

コメント