モンドリアン・スタイルの美しいステンドグラスの向こう側で、フェルメールの肖像画のような女性がこちらに目線を向けている、印象的なポスター画像。
モンドリアン・スタイルは無駄な曲線を排除して、真に重要な要素となる直線と色彩だけで構成されたアート。そして17世紀オランダの肖像画は表面的な美ではなく、人間の内面までも描写したことで高く評価されています。
その2つが重なり合い、まるで「合理性を追求した社会システムの奥に、覆い隠せない人間らしさが覗いている」…と連想させるような、映画のテーマと呼応したデザインです。
……とまぁ、何かそれっぽいことを書いてみましたが、映画本編についての感想は意外と人間くさくてシンプル。そんな深い考察とかも多分必要なく、わりとストレートに入ってくる映画です。
何より初見はアリシア・ヴィキャンデルの怪演に圧倒されて、あっという間に114分が過ぎていくこと請け合い(笑)見た目けっこうなオバサンが、3歳児になりきってるわけですからね。なかなかホラーな絵面ですよ…。
なんて脅かしつつも、映画「アセスメント~愛を試す7日間~」のネタバレ感想いきます。映画の一番肝のところをネタバレしてるので、本編未見の方はご注意ください。
鑑賞のまえに
2024年製作/ドイツ
時間/114分
監督/フルール・フォルトゥネ
出演/エリザベス・オルセン、アリシア・ヴィキャンデル、他
・お馴染み近未来ディストピアワールド。わりと近い将来こうなるかもというリアリティはある。
・見所はとりあえずアリシア・ヴィキャンデルの迫真の演技。「こっわ…」と思わせたあとのデレ要素もすごい。
・あまりご夫婦で鑑賞するのは進めません系映画。でもこれを一緒に見られたら、夫婦としてワンUPできる……かも。
あらすじ
資源が乏しく居住可能な土地が少ないために、出産に制限がかけられた管理社会。子どもを持つためには国から派遣された査定官による7日間の査定を受け入れパスしなくてなりません。ミアとアーリアンは国民の上位0.1%に属する優秀な夫婦であると認められ、念願の査定(アセスメント)を受けられることに。
2人のもとに訪れた査定官・バージニアが一見冷静で理知的な人物に見えるものの、査定が始まると夫婦が戸惑うような質問を投げかけ、さらに2人のプライベートな領域にまで踏み込んでいきます。そして2日目、キッチンに現れたバージニアはあたかも幼児のように振舞い…
感想
国家によって出産制限がかけられた近未来。
子どもを持つことは、高収入で高学歴、人格的にも優れたごくごく一部のエリートのみに許された贅沢となった世界。当局から派遣された審査官による査定(アセスメント)を受け、合格した夫婦のみが親になれる…というのがこの物語の大前提です。
そもそも何でこんなことになってるかというと、地球環境の変化によって資源や食糧が乏しくなり、無制限に増える人間全部を食べさせることができないからなんですね。
さらに国家体制に不満をもつ危険人物とみなされると、「旧世界」と呼ばれる過酷な環境の土地へと送られることになっています。もうジャンジャン頭数を減らしていかないと、快適な生活水準は維持できない。星新一の「生活維持省」を地でいく世界だということがよく分かります。
そして作中ではそこまで強調されていませんでしたが、この設定においておそらくは最も重要であると思われる要素がもう1つ。それは、ここが超超超高齢化社会であるということです。
テクノロジーが発達した結果、主人公のミアは植物学者として藻から自由自在に食糧をつくり出すことに成功し、夫のアーリアンはほぼ本物と変わらないバーチャルペットを生み出そうとしていました。どちらも人間にとって根源的な欲求である「食べたい」「愛したい」を満たすための研究です。より強くより多くのニーズを満たす能力を持っているからこそ、2人はこの社会でエリートでいられるんですね。
さて、それでは全ての人間にとって最も強く根源的な願望とは何か?
それは恐らく「死にたくない」ということでしょう。私はこの部分がこの映画を読み解く鍵になると思っています。
この世界では医療の発達も目覚ましく、すでに老化を遅らせて寿命を延ばす薬が開発されています。それさえ飲んでいれば150歳とか普通に生きられるわけです。
つまりどういうことか。地球環境が破壊されて住める土地も食糧も限られているという状況で、全然人間が減っていかないんです。年老いれば死んでいき、後進に場所を譲るという生き物としての当たり前の営みが止まってしまっている。すべては人間たちの「死にたくない」という欲望があまりに強かったために起きた不自然な状況。
さて、そこで主人公夫婦の人生を左右するアセスメント、子どもを持てるか持てないかをジャッジされる査定の話をもう一度考えてみましょう。
誰も死ななくなったから、人間が減らない世界。食糧がないのでペットは殺処分。人間も一見オシャレな生活をしているように見えて、実際には藻とか食べて飢えを遠ざけている現状です。
こんな状況で本当に人間を増やそうとするかなぁ?って話なんですよ。いや、もちろん現代の感覚なら「そりゃ子どもを持つのは生き物の当然の権利なんだから」となりますが、この徹底合理主義の管理社会において、成長して本当に生産性を上げられるという保証が何も無い存在を生み出すのか?という違和感。
そう、査定なんて実は真っ赤な嘘。
どうひっくり返っても「合格」はあり得ない。最初から「不合格」になると決まっている、とんでもなく大がかりな茶番なんです。夫婦の愛だの親になる資格だの、最初から試す気はゼロ。夢と期待に満ちて申し込みをしてきた夫婦に7日がかりで難癖をつけ、何とか不合格という既定路線に着地させるための「アセスメント」だったのです。
そのやり方は陰湿、かつ徹底的。名目上「査定官」を名乗る女性・バージニアは、無機質な態度で通りいっぺんの質問をして、各種の検査をして一応穏やかに初日を終えますが(まぁ、夫婦の寝室を覗き見するというびっくり査定も初日からありましたけど)、もう2日目からはエンジン全開でフルスロットルです。
ミアとアーリアンが朝キッチンで査定のことを話していると、そこに昨日の無機質な表情とは打って変わって奇妙に砕けた笑みを浮かべたバージニアがやってきます。まるで別人のようにだらしない姿勢で席につき、スプーンをオモチャにしたり、無意味にテーブルに塩をこぼして遊んだり……。
その様子に顔を見合わせたときのミアとアーリアンの「マジかよ……」という表情は秀逸。バージニアが幼児になりきって査定を始めていることを察し、ゴクリ…と唾を飲み込みます。完全に目だけで、これからの7日間の不穏な展開を物語っています。
「これはやらかしてくれそう」という観客の期待に応え、そこから幼児バージニアはやりたい放題暴れまくり、文字どおり家中を、そしてミアとアーリアンの夫婦関係をも破壊していくのです。
この「家族関係を辱めて家庭を破壊する」という行為には、何というか理屈ではない嫌悪感がありますよね。そういうの大好物な方、映画「ノックノック」のアナ・デ・アルマスほどではないにせよ、幼児バージニアもわりとあなたの期待に応えてくれると思います。
ワガママな振る舞いでミアとアーリアンが怒りを自制できるギリギリラインを狙ったり、逆にアーリアンだけにすり寄ってみせてミアを挑発したり(なかなか2人がアセスメントを放棄しないために焦ったバージニアはアーリアンと不貞行為に及ぶという暴挙にも)、ミアの大切な温室に放火して母親の形見の蘭の花を破壊したり…。えげつないよね…。「二度と子ども欲しいなんて寝言言わねーよーに思い知らせてやるよ!」と言わんばかりのやり口です。
後から理由は分かるのですが、バージニアも好きでこんなことやってるわけじゃないんですよ。国家権力に弱みを握られてて、何がなんでもアセスメントを不合格にしなきゃいけないっていう状況の中で追い詰められてるんです。
性格がひんまがってるのは、このアセスメントのシステムを考えた官僚たちでしょう。途中で何かミアとアーリアンの家にワケありの客ばかりが集められて、気まずーいディナーになるシーンもそう。
全員が国からの命令としてアセスメントのためにわざわざ集められた顔ぶれなんですが、2人が欲しくてしょうがない子どもをすでに手に入れているご機嫌な夫婦とか、ミアが昔不倫してた教授とか、アーリアンと関係の良くない空気読めない母親とか…っていうか、アーリアンの元妻でかつてアーリアンと2人でアセスメントに申し込んでた女性とか…。いやいや、絶対そんなメンツと一緒に和やかにご飯食べられないでしょ?
挙句の果てに、アセスメントのシステムを憎んでいるという1人の女性が、その場でいきなり持論をぶちまけ、場の空気を最悪なものにしてくれます。
「こんな身勝手に付き合わされるのは勘弁してほしい。子どもが欲しいなんて傲慢よ。あなたたちは『境界』ができる前のことを知らない。誰が後進のために席を譲れる?」
この100歳越えのオバサマが言いたいことは何かと言うと…平和ボケのお前らは知らんやろーけど、この世界は今でも生存競争の真っ只中なんだよ。誰か人を増やすなら、その分誰か他の人間が『境界』の外にある過酷な旧世界に送られて、1人分の席を空ける必要がある。私はこれからも長生きしたいし、あんた達だってそうなんでしょ?じゃあ子どもまで欲張らずに、もっと自分の命にしがみついとけよ…ってことなんです。
はい、このオバサマの言葉はこの世界の本質を突いてます。そして、これがまさにこの映画のテーマそのものだと私は思うんです。
あなたたちが欲しいものは何?子ども?それとも長寿?
本当に欲しいものは何ですか?
ということでしょう。
アセスメントは、その本質的な問いから新世界の住人たちの目を背けさせるために存在するとも言えます。「アセスメントに通りさえすれば、このまま長寿も子どもも両方手に入りますよ」という耳障りの良い嘘によって。
でも本当はそんなこと無理なんです。皆が長寿のままだったら人を増やせないから、新世界では子どもを諦めるしかありません。本気の本気で子どもを望むのであれば、生き永らえることが難しいと分かったうえで、旧世界に踏み出すしかありません。完璧に管理されて快適な暮らしが手に入る管理社会の外には、過酷な自然環境と向き合いながらも人間が自然のままの姿で生きる旧世界が広がっています。
ミアとアーリアンは、「私たちは子どもが欲しいんだ」と心を1つにしてアセスメントに臨んだつもりでいます。
でも実はそうではなかった。2人の望むものは、同じに見えて実は違ったのです。バージニアから査定不合格の結果を言い渡されたあと、ミアとアーリアンはまったく違った道を歩むことになります。
散々ボロクソにされた挙句に査定に落とされて怒りが収まらないミアは、どんな裏技を駆使したのかバージニアの素性を突き止めて彼女の住居に乗り込みます。このシーンは本当に印象的というか、意外でしたね。シュールでミステリアスな査定官・バージニアが人間らしい素顔を見せるというのは、この手のディストピア系では珍しい気が…。女性たちが苦しみながらも自分と向き合う姿を描こうとした監督の作風でしょうか。
しつこく食い下がられてキレたバージニアから、アセスメントなんて嘘っぱちだったと聞かされたミア。ショックを受け、バージニアに何でこんな仕事をしているんだと尋ねます。そこで明かされるバージニアの過去。
彼女は実はかなりの高齢で、おそらく境界ができる前の世界で子どもを産み、そしてその子を事故で失ったという過去を持っていました。「もう一度母親になりたい。我が子を腕に抱きしめたい」という願望に突き動かされて、査定官を続ければ人口制限が緩和されたときに子どもを持つことが許されるという国家の言葉を信じて働いていたのでした。
そう、バージニアの本当の姿は、子どもを切望して査定を受ける女性たちと同じ。いえ、バージニアいわく、実際に母になる喜びを知っている分だけ彼女の願望のほうが強く切実なものなのです。
あんなに憎んでいた査定官が、自分と同じ希望にすがって心を殺して残酷な仕事をしていたのだと知って呆然とするミア。アセスメントの最中、バージニアに感じていたシンパシーの正体は、バージニアの側から発せられる「私は本当はあなたと同じなのよ」という心の叫びの反響だったのかもしれません。
「旧世界なら子どもが望めるんでしょ?どうしてここを出ていかないの?」と問うミアに、バージニアは寂しそうに微笑みます。自分はもう高齢で、延命薬で命をつないでいる状態だから、旧世界では生きられない。ここで査定官をやることだけが唯一の希望なのだと。
「査定官を続けていれば、子どもを持たせる」なんて真実なわけがないと、心のどこかで分かっていても。アセスメントの嘘を知っているバージニアだからこそ、そのことは痛いほど分かっていたのでしょう。
だからこそ、ミアと心を割って話した後に、ついにバージニアは窓から飛び降りて自殺してしまいます。ミア達のアセスメントの途中にもバージニアがまるで自分から死を望んでいるかのような描写が度々ありましたが、アセスメントで不合格を言い渡すたび、彼女自身も「子どもは持てないのだ」という事実を突き付けられるようでずっと辛かったのでしょうね。
もう年齢によって子どもを望めない身体のバージニアは旧世界に飛び込むことができず、自らの死で叶わない願望にケリをつけます。
そしてミアは…自然に子どもを授かるという可能性に賭け、映画の最後で新世界の暮らしを捨てて旧世界に足を踏み入れました。彼女がずっと心から欲しがっていたもの。それは「母と子の間にある、本当の愛」だったのだと思います。
彼女には、まだ子どもだった頃に母から愛されたという記憶がありました。そのことは映画の冒頭の海のシーンであり、彼女が心から大切にしていた母の形見の蘭の花、そして査定の最初の質問での「なぜ子どもが欲しいのか」という問いに対して「帰属意識を与えてあげたいから」という答えに表れています。母から与えられた愛の実感を、次は自分が子どもに渡したい。それこそが「子どもを持つ」という行為の最も根源的な動機になるのではないでしょうか?
一つの世代がいつまでも死なずにいれば、内面から腐っていくだけ。命は生まれて消えていく。けれど愛は世代間で受け継がれ、半永久的に生き続けることができるのです。
その循環の中に飛び込んでいったミアと対照的なのが、アーリアンの選択です。映画の最後、彼は自らのバーチャルペットの技術を応用して、何とバーチャル家族を生成してしまい、その幻想の中で生きることを選んでいました。
「子どもが欲しい」という表面的な願望の下にあったもの。それは、ミアにとって「母からもらった愛を次の世代に渡したい」という衝動で、アーリアンにとっては「家族に囲まれているという安らぎや安心感」だったのでしょう。あまり女だから男だからという括りでは語りたくありませんが……でも、そこには何らかの生物学的な違いがあるのだと感じてしまいます。
あるいはアセスメントで炙り出された「本当に欲しいものは何なのか?」という問いに対する答えこそが、「親になる資格」の有無を決定づけるものなのかもしれません。
少し重たいテーマではありますが、シンプルに近未来SFものとしても楽しめる良作です。ちなみにこれによく似た世界観の小説「世界でたった一人の子」もおすすめ。胸が締め付けられるような描写もありますが、この映画よりも明るく希望を感じさせるラストで読後感は爽やかですよ!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました♪

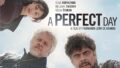
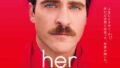
コメント